弘済 みらい園・のぞみ園の日常を綴ります。
水耕いちごサイダー
2022年08月12日(金曜日)
この度、「株式会社いちご研究室」様より、いちごサイダーの寄贈をいただきました。-e1660276954810.jpg)
水耕栽培でいちごを生産されている企業様です。
完全無農薬で、人にも環境にも優しいいちごだそうです。
どんな味がしたのか気になります。
本当にありがとうございます。
キャンプのお供に
2022年08月12日(金曜日)
例年、トロピカルジュースを寄贈いただいている「協同食品株式会社」様より、今年も、グァバジュースとマンゴージュースをいただきました。
ちょうど夏休みで、各フロアがキャンプに行く時期と重なることが多く、キャンプへ持っていくフロアもあります。ほかに、夏のスイーツ作りに使うことも。
夏の楽しみの一つです。
本当にありがとうございます。
びっぐはーと
2022年08月12日(金曜日)
例年、園より希望した物品を寄贈いただいている「げんきvillage」様が、今年もたくさんのワガママを聞いてくださいました。
いつも、とにかく何でも言ってください、と大きな心で受けてくださるのをいいことに、本当にいろんな物をお願いしています。
げんきvillage様の心意気に賛同して、お力添えをいただいている皆様にも、本当に感謝しております。
いただいた物品たちは、掃除機は子ども達が自分の部屋をお掃除する際に。自転車は学校や塾の行き帰り、ちびっ子の練習用に。オーブンレンジは、子ども達とお菓子を焼いたり。歌うのも踊るのも、音楽が好きな子にはラジカセ。と、いつも大活躍です。
厚かましくも、次回へ向けて、お願い事をたくさん考えております。





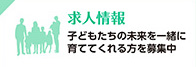
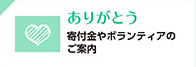


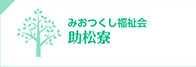
.jpg)
.jpg)
